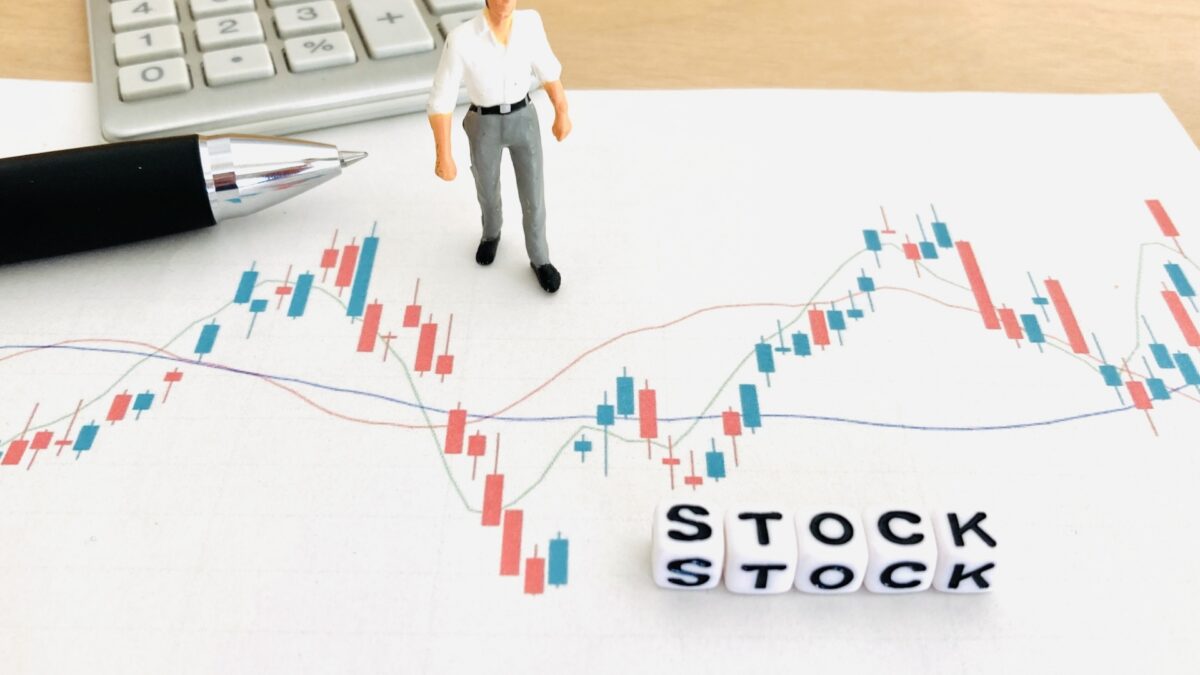Ethereum財団は、分散型金融(DeFi)分野への取り組みを強化する一環として、新たに設立したマルチシグウォレットに50,000ETHを移動した。このウォレットは、オンチェーン資産保管プロバイダー「Safe」による3-of-5形式で管理され、最初のトランスファーはDeFiプロトコル「Aave」を通じて実施された。
この動きは、財団がETH売却に対する批判に直面する中で行われたもので、資産の売却を避ける新たな収益モデルを模索していることを示唆する。同時に、共同創設者ヴィタリック・ブテリンの発言によれば、ステーキングオプションが今後の戦略の一部として検討されているという背景もある。
ビットコインの市場上昇が注目される一方で、Ethereum価格の低迷が続く中、同財団の動向はEthereumネットワークの成長と安定性にどのような影響を及ぼすのか、関心が寄せられている。
Ethereum財団のマルチシグウォレット設立が示すDeFiへの本格参入

Ethereum財団は新たに設立したマルチシグウォレットを通じ、分散型金融(DeFi)分野への関与を一層深めている。このウォレットは3-of-5形式で設定され、オンチェーン資産保管プロバイダーである「Safe」によって管理されている。この形式により、ウォレットのセキュリティは強化される一方で、アクセスにおける柔軟性も確保されている。
また、最初の50,000ETHはDeFiプロトコル「Aave」を通じてライブ状態にある。この動きは、Ethereumネットワークの成長に必要な資金を新たな形で運用する試みと見られる。同財団の公式発表によれば、さらなる資金の追加が段階的に進められる計画である。これにより、財団がDeFiエコシステムの利用価値を実証しつつ、ネットワークの資産活用を高める可能性が示唆される。
Ethereum財団のこうした取り組みは、単なる技術革新にとどまらず、DeFiが従来の金融システムを超える可能性を示している。財団の行動が今後の市場に与える影響は注目に値する。
ETH売却批判を背景に浮上する新たな収益モデルの模索
Ethereum財団が資産を売却して運営資金を賄う手法には、一部の保有者からの批判が根強い。特に、Ethereum価格の低迷が続く中での売却は市場への影響が大きいと指摘されている。これに対し、財団はETH売却に依存しない収益モデルの構築を模索している。
その一環として注目されるのが、ステーキングの導入である。ヴィタリック・ブテリン氏は「X」で、これまで規制上の懸念やネットワークのハードフォーク時の中立性維持が課題であったとしながらも、財団がステーキングの可能性を再評価していることを明らかにした。これにより、財団が保有するETHの価値を長期的に維持しつつ、安定した収益源を確保することが期待される。
ステーキングの導入が実現すれば、Ethereumエコシステム全体に信頼感を与えるとともに、財団が市場の不安定性に左右されにくい運営を確立する一助となる可能性がある。
Ethereum財団の行動が示す市場への影響と今後の展望
今回のマルチシグウォレット設立やETH売却回避の動きは、Ethereum財団が市場の変動に対して柔軟に対応しつつ、エコシステム全体の成長を意識していることを物語っている。一方で、Ethereum価格の低迷やETH売却の問題は、投資家心理に影響を与え続ける課題として残されている。
ビットコインが史上最高値を更新する中、Ethereumは競争相手としての地位を維持するために、新たな戦略を打ち出す必要に迫られている。財団によるDeFi分野への注力は、こうした課題を克服するための重要なステップである。
市場の反応次第では、今回の取り組みがEthereumネットワークの将来的な方向性を左右する可能性がある。特に、DeFiエコシステムにおける財団の役割がどう進化していくかが、今後の注目点となるだろう。
Source:crypto.news